Windows10に古いグラボを認識させる。
2016.10.06
ドライバの強制更新のせいでi5のオンボードVGAにトラブルが出ているのが
身近に結構あります。i7は知らない( ´艸`)
古いドライバにすることで一時期はしのいだのですが、
最近のWindowsアップデートによって、古いドライバーでも止まってしまう症状が
出始めています。
そこでオンボードVGAとはオサラバして、適当なグラボを挿して
トラブル回避しようと考えたですが、
手元にある適当なグラボがRadeon X1650Proです(笑)
Windows10に対応どころかWindows7にすら対応してません。
ラストOSはVistaですね。
こいつを自動で認識させようとした場合、
適切なドライバーを見つけられないので
入れることができません。
AMDからVista用のドライバを落としてきてインストールしようとしても、
インストーラがボードを認識してくれないので、セットアップが途中で止まります。
提供されるドライバは圧縮ファイルで、展開先がc:\atiなのですが、
Windowsのドライバの更新で強引にそこを指定し、組み込もうとすると、

こんなエラーで落ちてしまうのです。
試行錯誤して、最適解を見つけましたが、わかってしまうと実に簡単です。
ATI系ドライバーの残骸は全てアンインストールした後
AMDからダウンロードしたファイルを実行。
ボードを認識できずセットアップは終了するのですが、
c:\atiの階層の中にあるSetup.exeを見つけ、コイツのプロパティを開き、
互換性タブから、互換モード、Windows Vista(Service Pack2)を選んで、適用するだけ。
あとはこのSetup.exeを実行すればボードを認識して問題なくセットアップされます。
身近に結構あります。i7は知らない( ´艸`)
古いドライバにすることで一時期はしのいだのですが、
最近のWindowsアップデートによって、古いドライバーでも止まってしまう症状が
出始めています。
そこでオンボードVGAとはオサラバして、適当なグラボを挿して
トラブル回避しようと考えたですが、
手元にある適当なグラボがRadeon X1650Proです(笑)
Windows10に対応どころかWindows7にすら対応してません。
ラストOSはVistaですね。
こいつを自動で認識させようとした場合、
適切なドライバーを見つけられないので
入れることができません。
AMDからVista用のドライバを落としてきてインストールしようとしても、
インストーラがボードを認識してくれないので、セットアップが途中で止まります。
提供されるドライバは圧縮ファイルで、展開先がc:\atiなのですが、
Windowsのドライバの更新で強引にそこを指定し、組み込もうとすると、

こんなエラーで落ちてしまうのです。
試行錯誤して、最適解を見つけましたが、わかってしまうと実に簡単です。
ATI系ドライバーの残骸は全てアンインストールした後
AMDからダウンロードしたファイルを実行。
ボードを認識できずセットアップは終了するのですが、
c:\atiの階層の中にあるSetup.exeを見つけ、コイツのプロパティを開き、
互換性タブから、互換モード、Windows Vista(Service Pack2)を選んで、適用するだけ。
あとはこのSetup.exeを実行すればボードを認識して問題なくセットアップされます。
Win10アップデート後、Excelの画面が崩れる
2016.10.06
先月末にWindows10の大型アップデートが走りましたが、
これにより、Excel2007で画面が崩れる症状がでています。
2013では今のところ症状は出ていません。
セルの結合を行った部分に灰色の色が付いたり、
罫線がセルとは関係ないところについたり、
スクロールに描画が追い付いてないとか、仕事に影響が出るレベルです。
Officeをインストールし直したり、Excelの設定を変更したりして、
いろいろ試しましたが、結果全く関係ないと思われる場所が原因でした。
Windows10の設定から、デバイス(bluetooth、プリンター、マウス)に入って、

↑「Windowsで通常使うプリンターを管理する」この部分をオフにするのです。
これでひとまず落ち着きます。
同じトラブルで悩んでいる人はお試しあれ。
これにより、Excel2007で画面が崩れる症状がでています。
2013では今のところ症状は出ていません。
セルの結合を行った部分に灰色の色が付いたり、
罫線がセルとは関係ないところについたり、
スクロールに描画が追い付いてないとか、仕事に影響が出るレベルです。
Officeをインストールし直したり、Excelの設定を変更したりして、
いろいろ試しましたが、結果全く関係ないと思われる場所が原因でした。
Windows10の設定から、デバイス(bluetooth、プリンター、マウス)に入って、

↑「Windowsで通常使うプリンターを管理する」この部分をオフにするのです。
これでひとまず落ち着きます。
同じトラブルで悩んでいる人はお試しあれ。
3D-PRT26)キャリッジが届いた!
2016.09.22
先日ブログを更新して、翌日にはエフェクター、さらに昨日キャリッジが届きました。
お思いのほか到着が早かったです。
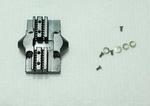

商品紹介ではよくわからなかったのですが、
ベルト止めワッシャーがM2ワッシャーと同サイズなんですが、
穴が一般的なM2ワッシャーより何故か大きすぎます。
辛うじてすっぽ抜けないレベルの穴で、安定感なく気持ち悪いです。
あえて特殊なワッシャーにしているかもしれないので、後から研究してみますが、
一般的なM2ワッシャーに交換したほうが気持ち的に落ち着きそうです。
エフェクターのホットエンド固定具はセットでないものがほとんどです。
付属しているか不明な場合は、送料込み100円くらいなので一緒に買っておくといいと思います。
買い忘れるとまた2週間ほど待たされます。
キャリッジのサイズを測ってみました。



うーん、思っていたのと違う・・・ 結構個体差があるのですね。
それでも3Dプリンターで印刷したものと比べると精度のケタが1つ違います。
厚みに関しては最大と最小の差が0.02mmなので
望み通りです。穴と穴の間が、各キャリッジと比べて最大0.05mm違うので
これがどう影響するか興味があります。
あと印刷に大きく影響が出そうな、穴の位置ですね。
私の持っている道具では正確に測れないのが残念です。
下にエフェクターのサイズを載せてますが、
穴と穴の距離が最大0.1mm違って結構適当です(笑)



大きく変わってしまうので、調整をまた最初から行わないといけませんね。
お思いのほか到着が早かったです。
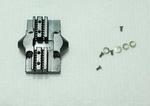

商品紹介ではよくわからなかったのですが、
ベルト止めワッシャーがM2ワッシャーと同サイズなんですが、
穴が一般的なM2ワッシャーより何故か大きすぎます。
辛うじてすっぽ抜けないレベルの穴で、安定感なく気持ち悪いです。
あえて特殊なワッシャーにしているかもしれないので、後から研究してみますが、
一般的なM2ワッシャーに交換したほうが気持ち的に落ち着きそうです。
エフェクターのホットエンド固定具はセットでないものがほとんどです。
付属しているか不明な場合は、送料込み100円くらいなので一緒に買っておくといいと思います。
買い忘れるとまた2週間ほど待たされます。
キャリッジのサイズを測ってみました。



うーん、思っていたのと違う・・・ 結構個体差があるのですね。
それでも3Dプリンターで印刷したものと比べると精度のケタが1つ違います。
厚みに関しては最大と最小の差が0.02mmなので
望み通りです。穴と穴の間が、各キャリッジと比べて最大0.05mm違うので
これがどう影響するか興味があります。
あと印刷に大きく影響が出そうな、穴の位置ですね。
私の持っている道具では正確に測れないのが残念です。
下にエフェクターのサイズを載せてますが、
穴と穴の距離が最大0.1mm違って結構適当です(笑)


大きく変わってしまうので、調整をまた最初から行わないといけませんね。
 2016.10.06 17:03
|
2016.10.06 17:03
| 








