Office Home&Business Premium で「お待ちください」が続く問題
2018.01.23
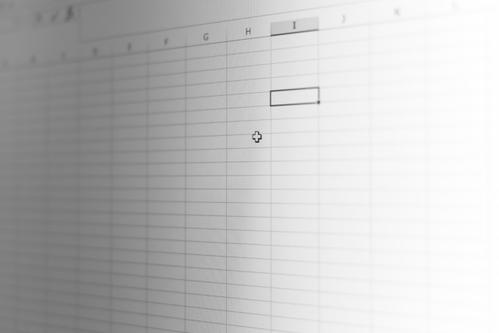
タイトルの通りなのですが、
お客様先で初期セットアップを行う際に
一番困るのが、ネット回線が遅いことで固まる現象。
特にOffice Premiumの等でのライセンス認証です。
おそらく最新版のプログラムをダウンロードしに行っているのだと思いますが、
ガラガラ時間の光回線ではそれほど待たずに次のステップに進めますが、
ADSLなんて使っていると次の日になっても終わりません。
これを回避する方法として、MSから出されている提案がこちら。
https://support.microsoft.com/ja-jp/help/4051716/please-wait-displayed-indefinitely-when-office-premium-is-installed
まず先に認証だけ済ませちゃおう的なものですね。
起動時に現れる認証を閉じた後、ExcelやWordを文章が打てる状態にしてから
ライセンス認証に飛ぶとアップデートを拾わずに認証終了できるようです。
途中からいつもの「お待ちください」に切り替わって
また待たされるのか?と思いましたが、数秒で次のステップに行きました。
これでかなりの時間短縮になりますなぁ(๑´ڡ`๑)
KB4056894で再起動ループする問題
2018.01.21
今日対応したトラブルですが
Windows7でKB4056894をあてると再起動を永遠に繰り返すという
実質パソコンが使えなくなる問題。
セーフモードに切り替えると、
失敗を検知し自動的にアンインストールが走るのですが、
通常起動するとまた自動更新で入ってくるので、
結局トラブルは永遠に続きます。
ダウンロードファイルが破損しているわけでもなく、
WindowsUpdateを使わず手動でダウンロードしてアップデートしてみても
同じ症状に見舞われます。
対処方法は問題が解決するまで
KB4056894をインストールしないことが一番。
とりあえず自動アップデートしないようにして対応しましたが
どうやら巷ではじわじわ浸透しているようで、ネット上では原因が判明していましたよ。
DiXiM系ソフトとの相性が発生。
AMD系CPUを使っているハードで発生
Windows7では上記の条件で発生するようです。
DiXiMを提供する会社では意外と早く対応したようですね。
http://www.ask-support.com/?p=1395
パッチが出たのでこちらを入れることで対処できそう。
今度行ったときに対応しよう。
Windows7でKB4056894をあてると再起動を永遠に繰り返すという
実質パソコンが使えなくなる問題。
セーフモードに切り替えると、
失敗を検知し自動的にアンインストールが走るのですが、
通常起動するとまた自動更新で入ってくるので、
結局トラブルは永遠に続きます。
ダウンロードファイルが破損しているわけでもなく、
WindowsUpdateを使わず手動でダウンロードしてアップデートしてみても
同じ症状に見舞われます。
対処方法は問題が解決するまで
KB4056894をインストールしないことが一番。
とりあえず自動アップデートしないようにして対応しましたが
どうやら巷ではじわじわ浸透しているようで、ネット上では原因が判明していましたよ。
DiXiM系ソフトとの相性が発生。
AMD系CPUを使っているハードで発生
Windows7では上記の条件で発生するようです。
DiXiMを提供する会社では意外と早く対応したようですね。
http://www.ask-support.com/?p=1395
パッチが出たのでこちらを入れることで対処できそう。
今度行ったときに対応しよう。
Z4タブレット SO-05G バッテリーが限界
2018.01.15

うちのZ4タブレットのバッテリーが危うい。
ネットや写真等を見るときは50%くらいで電源が落ち、
ゲームをしようものなら90%くらいで落ちる。
USBから給電しながらであれば落ちないので
今は輸血プレイがデフォルトになってます。
これを買ったのが2015年07月末
ということは2年半。
ゲームも頻繁にやって2年半ならもった方かな(;´Д`)
ということでドコモにバッテリー交換のお願いに行きました。
グローバル版をソニーに出した場合は
部品工賃込みで12,000円と明記されているので
ドコモ版も大差ないだろうと思って行ったのです。
ですが、ちょっと予想とは違ったので驚きでした。
・見積もり結果は10日~2週間かかる。修理はさらに1週間追加。
・見積もり料金は無料。
・ドコモショップでは個人情報をお預かりできないので、
お客様の前で初期化作業を行ってから見積もりに出す。
・バッテリーは修理扱いで、他におかしい所が少しでもあれば
全て交換されるため、バッテリーのみの依頼でも
料金は跳ね上がることがある。
・修理の上限価格は約7万
少しでもおかしい所があれば全修理という話は
ボタンが少し緩いとかでも交換になるらしい。
ウチのはUSBポートが少し甘い気がするので
交換対象になりそうだわ(;´Д`)
液晶にヒビが入っている人はそれも交換になるので
ハンパない額になりそうですね・・
3週間手元に無いのも不便だし、
バッテリーだけ交換したいのに、
見積もりだけでアカウント情報から
何から全部消されるのも嫌だなぁ。
まぁ消されても困らないけど入れ直すの面倒(;´Д`)
というわけで一旦持ち帰ってきましたよ。
まず、ドコモ以外で交換できる業者をネットで調べてみます。
結果:なし
なぜ?(;´Д`)
修理は受け付けるけどバッテリーは交換できないと断る業者もありました。
なら、バッテリーを自分で交換することを考えてみました。
でも、売っているところは国内ではまったく見つからない。
参った(´;ω;`)
いつも利用しているAliExpressでも調べてみると

https://ja.aliexpress.com/item/xperia-z4-SGP771-SGP712-1291-0052-LIS2210ERPX-LIS2210ERPC-3-8-2/32835739164.html
有りましたわ。1件だけ。
これタイトルに正規品で新品と書いてるけど不安(;´Д`)
一応「本当に正規品なの?」ってメールを送ってみると
「私たちは正規品を売っています。本当です。
私たちはSony等のメーカーにバッテリーを供給している業者です。
メーカーには供給を終了したバッテリーなので現在はわかりませんが、
その後にタブレットに大幅な仕様変更がされていなければ
一致するはずです。」
という返事。
Z4タブレットが登場した時、すぐに分解レビューしているHPが有りましたが、
そのとき写っているバッテリーの型番がLIS2210ERPX
この業者が販売しているバッテリーもLIS2210ERPX
言っていることは正しいようです。
送料いれて5,690円
偽物が届いたらAliexpressからOpen Disputeすればいいし、
少しだけ不安が晴れたということで、
まいっかという気分に。
ということで注文してみましたよ。
届いたら交換記事書きますかね。
 2018.01.23 18:01
|
2018.01.23 18:01
| 








